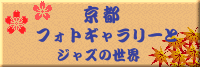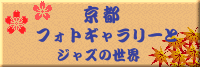
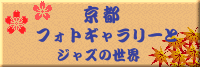

通し矢とは「的に当たった矢」という意味で、本堂西側の軒下 幅2.5M 高さ5.5M 長さ120M を南から北へ射通す競技でありました。
一昼夜のうちに何本的に当てられるかを競ったと伝えられています。
慶長11年(1606)に開かれた大会では、尾張清洲藩松平家中の浅岡重政が51筋射を通し、家康から「天下一」の称号を許可されました。
記録的には明暦2年(1656年)紀州の吉見台右衛門が6343本を、次いで寛文2年には尾州の星野勘左衛門が6666本を通して「天下一」を名乗ったが、寛文8年(1668年)には、紀州
葛西園右衛門が7077本を通して「天下一」を奪取しました。
これに対して、翌9年5月2日 星野勘左衛門は再度挑戦し総矢10542本中正午までに8000本を通して葛西の記録を塗り替え「惣一」を手中にし、今だ余力を残しながら「打ち止め」にした。
この記録は長らく破られることはなかったが、貞亨3年(1686年)4月27日、紀州の和佐大八郎は弱冠18歳で総矢13053本中、8133本を通し先の勘左衛門の記録を凌駕し通し矢史上不朽の大記録を打ち立てました。これは1分間に約9本、命中率62%と驚異的な記録です。
通し矢は従来1月15日に行われていましたが成人の日が不定になり小正月に近い日曜日に行われます。
当日は三十三間堂も無料拝観になります。
 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
 5 |
 6 |
 7 |
 8 |
 9 |
 10 |
 11 |
 12 |
 13 |
|
 14 |
 15 |
 16 |
 17 |
 18 |
 19 |
 20 |
 21 |